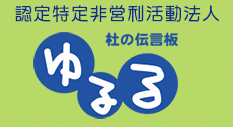高校生が「伝える」側に挑戦 ―3.11メモリアルネットワークでの3日間の夏ボラ体験―
8月22日、3.11メモリアルネットワークの活動拠点「MEET門脇」を訪れ、ここで夏ボラ体験をしている高校2年生の玉澤七帆さんと、虎歩霞さんにお話を伺いました。
2人は、夏ボラ体験1日目・2日目に、震災遺構の門脇小学校を見学したり、語り部の方々から話を聞いたりして学びを深めました。取材に訪れた、体験3日目のこの日、2人はこれまでに学んだことを生かし、自ら原稿や構成を考え、施設内を案内する初のガイド役に挑戦しました。
「自分が覚えていることを生かしたい」—玉澤さん
玉澤さんは震災当時2歳。保育所から先生の車で避難した記憶などが残っているそうです。「自分が覚えていることをこのボランティアに生かせると思って参加した」と話します。ガイドでは、震災当時に石巻日日新聞が手書きで発行した「壁新聞」を紹介。「壁新聞は戦時中以来の取り組みだった」と説明しながら、伝えることの重みを感じていたようでした。初めてのガイドを終えた後は「原稿を飛ばしてしまったりして思うようにできなかった」と悔しさも口にしましたが、震災を語り継ぐ責任感を背負う姿がありました。
「知らなかったことを知りたい」—虎さん
石巻出身である虎さんは、震災発生当時、両親の仕事の都合で茨城に住んでいたそうです。今回の夏ボラ参加の理由は、「石巻が地元でありながら地元で何が起きたのかを知らない」という思いからでした。ガイドでは南浜地域の被災前後の航空写真などを解説。「緊張で声が震えた」と振り返りつつも、ガイドの最後には「災害をなくすことはできないけれど、事前の対策が大切。一人の行動がみんなを助ける。行動力を大切にしたい」と語りました。
2人は、午後には埼玉から訪れた高校生に向けてもガイドを担当。虎さんは「高校生は周囲から頼られる年齢。冷静な判断と行動力を大切にしてほしい」と、同世代にメッセージを送りました。
その言葉には、体験を自分のものとして受け止めた実感がにじんでいました。
震災から14年。
記憶の風化が懸念される中、今回未来へ語り継ぐ役割を担ったのは、「知らなかった地元」を学び直そうとする、2人の高校生でした。
彼女たちが夏ボラを通して学んだことを生かしながら語った一言一言は、聞く人の胸に深く届いたと思います。2人の挑戦は、震災を知るだけでなく「自分の言葉で語り継ぐ」ことの大切さを改めて教えてくれました。(杜の伝言板ゆるるインターン・廣田朱里)